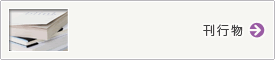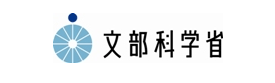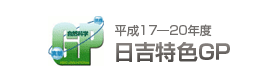アルコール発酵 (b)
発酵という現象は、微生物内の酵素による化学反応であることを学ぶ。またその最適温度を調べる。
実験風景
*写真をクリックすると大きくなります。
- (lightboxで画像ウインドウが開きます)
乾燥酵母とスクロース液、およびシリコンチューブをつけた注射筒
- (lightboxで画像ウインドウが開きます)
スクロース酵母液を注射筒に吸い上げているところ
- (lightboxで画像ウインドウが開きます)
注射筒内で(室温で)発酵させ、発生した気体の体積を一定時間毎に測定しているところ
- (lightboxで画像ウインドウが開きます)
ウォーターバススターラーを使って、高温での発酵速度を測定しているところ
- (lightboxで画像ウインドウが開きます)
実験室の様子
- (lightboxで画像ウインドウが開きます)
発酵後のスクロース酵母液をろ過し、その糖度を測定しているところ
実験の紹介
実験の目的とねらい
スクロース(ショ糖)は酵母の嫌気呼吸によってエタノールと二酸化炭素へ変化する。この反応速度が温度によって異なることを確かめる。(酵素反応には最適 温度があり、温度が低すぎても高すぎても反応が遅くなる)。また、二酸化炭素発生量と糖度低下との量的関係を考察する。これにより、発酵という現象が酵素を触媒とした化学反応であることを学ぶ。
実験内容
酵母とスクロースの混合液を一定量だけ注射筒に入れ、発生する気体の体積の時間変化を追跡する。室温だけでなく、湯浴を使って温度を上げた場合も測定す る。発生した気体に石灰水を加え、二酸化炭素であることを確認する。発酵による糖度の低下も確認する。また、ヨードホルム反応を用いて、エタノールの検出を行なう。
実験上の注意
<実験開始前の準備>
[使用器具および試薬]
・ウォーターバス
・糖度計
・タイマー
・電子天秤、薬包紙
・50 ml ガラス製注射筒(ルアーロック先)
・30 ml プラスチック製注射筒
・ルアーフィッティング(プラグおよびテーパー)
・シリコンチューブ(内径3 mmφ、外径5 mmφ、長さ30 cm)の片側にテーパーをつけたもの
・シリコンチューブ(長さ5 cm)の両端にテーパーをつけたもの
・ろ紙
・5 %スクロース水溶液
・乾燥酵母(市販されているパン用のもの。開封後は、冷蔵冷凍保存する)。
・メスシリンダー
・飽和石灰水
・ヨウ素液
・ヨードホルム
・定規
・個人器具および机上試薬
[溶液の調製]
ヨウ素液は、ヨウ素0.6 gとヨウ化カリウム1.5 gを水15 mlに溶かす。(ヨウ素がやや溶けにくい)。
スクロース水溶液を追加で調製する場合、元の溶液と新しい溶液の濃度を厳密に一致させておくこと。(そうしないと、発酵前の糖度が2種類となり、混乱が生じる)。
<実験開始時の注意>
・酵母スクロース液を注射筒で吸い上げる前に、液をよく撹拌する。(酵母が沈殿してくるため)。
・酵母液は味噌くさいので、こぼしてふき取った紙などは回収する。
・使用する糖度計の精度は±0.2。
・発酵後のスクロース酵母液をろ過するときに、ろ紙を水でぬらしてはならない。
<失敗例>
・反応速度と温度との関係が不明確な結果となった。(原因:酵母スクロース液をよく撹拌せずに使ったため、酵母の濃度が同じでなかった)。
・60℃での測定であるのに、途中で発酵が止まっていない。(原因:実験開始直前にビーカー内のお湯をバス内のものとよく交換していない。あるいは、目盛りを読むときに注射筒をお湯から出している)。
・発酵後の糖度が異常に低くなった。(原因:スクロース酵母液をろ過する際に、ろ紙を水でぬらしてしまった)。
実験テーマの履歴など
慶應義塾大学日吉キャンパスの文系学生を対象とする化学実験において、この実験テーマは2007年に開始されました。
この実験テーマを始めるに当たっては、文献(1,2)の内容をベースにしました。なお、酵母を使ってブドウジュースなどを発酵させることもできます(3)。
参考文献
(1)「新版 生物ⅠB」pp.83-85. (実教出版2001年).
(2) 鹿児島県総合教育センター「指導資料 理科」第240号 微生物による化学反応(2003年).
(3) 群馬県総合教育センター「教育研究(平成13年度)」アルコール発酵の簡単な実験.
(4) 大橋敦史、福山勝也、大場茂「アルコール発酵の最適温度の測定」、慶應義塾大学日吉紀要、自然科学No.45, 1-13 (2009年).
実験テキスト
- アルコール発酵
 (358KB)
(358KB)